ダイエットの停滞期とは?挫折のきっかけとなる停滞期を乗り越える方法
2020/3/10

ダイエットを始めてから順調に体重が減っていたのに、急に減りにくくなった場合は停滞期に入った可能性があります。停滞期には、ダイエットのモチベーションが下がったり、栄養の吸収率が上がったりすることで、ダイエットの失敗につながりかねません。ダイエットを成功させるために、停滞期の正しい知識と乗り越える方法を身につけておきましょう。ここでは、ダイエット中の停滞期の仕組みや時期、対処法について詳しくご紹介します。
ダイエット中に起こる停滞期とは

停滞期とは、これまで順調に減っていた体重が減らなくなり、停滞する時期のことです。停滞期の仕組みや起こり得る問題について、詳しくみていきましょう。
停滞期に起こる問題
停滞期になると、同じダイエット法を続けているのに、これまでよりも体重が減りにくくなります。停滞期は、安静時の消費エネルギーとなる「基礎代謝」が低下しているため、このタイミングでダイエットをやめるとリバウンドする可能性があります。停滞期は、人の身体に備わる「ホメオスタシス機能」が原因です。
ホメオスタシスとは、体温や血糖値などを正常に保とうとする機能のことで、ダイエットによって飢餓状態に近い状態となることで働き始めます。そうなると、栄養の吸収率が高まったり、脂肪が蓄えられやすくなったりするため、体重の減少が停滞するのです。
停滞期に入る時期
「ダイエット開始から1ヵ月前後」、もしくは「体重が5%減少した」これら、どちらかのタイミングで停滞期に入るといわれています。ただし、停滞期に入る時期には個人差があるため注意が必要です。また、停滞期は1ヵ月前後続くとされています。
停滞期に入ったときの対処法

停滞期の影響を最小限に抑えるために、次のように対処しましょう。
焦ってダイエットの内容を変えない
体重が減らなくなったことに焦り、過度な食事制限や激しい運動をすると、かえって停滞期から抜け出せなくなります。ますます飢餓状態が進むため、ダイエットの内容を変えないことが大切です。
栄養バランスのいい食事を心がける
栄養バランスのいい食事は、ダイエットの基本です。特定の食べ物を多く食べても、停滞期からは抜け出せません。栄養バランスのいい食事を続けることで、停滞期によるダイエットへの影響を抑えられます。
ダイエットを継続する
停滞期にダイエットをやめると、吸収率が高い状態で摂取カロリーが増えるため、リバウンドする恐れがあります。停滞期に入っても、ダイエットは継続することが大切です。
チートデイを作る
カロリーを普段以上に摂る「チートデイ」を作ることで、停滞期から抜け出せるという説もあります。
チートデイを作ると停滞期から早く抜け出せる?

実際のところ、チートデイを作ると停滞期から早く抜け出せるのかどうか詳しくみていきましょう。
チートデイはエネルギーを十分に摂る日のこと
チートデイとは、エネルギーを十分に摂ってもいい日のことです。停滞期に入ってからチートデイを設けることで、身体が飢餓状態から脱したと判断し、停滞期から抜け出せるといわれています。
チートデイのメリット
チートデイによって停滞期から抜け出すことができれば、基礎代謝が上がり、再び、体重が減りやすくなることが期待できます。また、我慢していた食事を十分に摂れることでストレスが軽減される可能性もあるでしょう。
チートデイの取り入れ方
停滞期に入る時期には個人差があるため、停滞期に入ったと感じてからチートデイを設けましょう。チートデイの日数は1日です。摂取カロリーが多い日が続くと、体重が増えてしまうでしょう。
チートデイの過ごし方
チートデイであっても、寝る前に食事しないことが大切です。寝る前に食事をとると、摂取したエネルギーを消費できず、太ってしまうでしょう。また、炭水化物や脂質に偏った食事や大量に摂ることも避けてください。
停滞期を抜け出すためとはいえ、多量のエネルギー摂取はリバウンドを招く可能性があります。また、チートデイが停滞期から早く抜け出す効果があるかどうか、賛否が分かれていることも覚えておきましょう。
ダイエットの停滞期を正しく過ごそう!

停滞期に入ると焦って食事量を減らしたり運動量を増やしたりしがちですが、これまで通りのダイエットを続けることが大切です。また、クリニックで「メディカルダイエット」を試してみるのもいいでしょう。
メディカルダイエットとは、医師の管理のもと、内服薬や注射、医療機器などを用いて、無理せず行える治療方法です。
食事制限や運動とあわせることで、効率的にダイエットできるでしょう。過度な食事制限は、ダイエットの失敗やリバウンドの原因になるため、メディカルダイエットをうまく活用することをおすすめします。
監修者
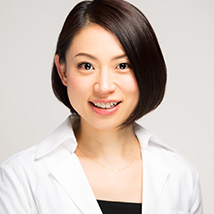
河村優子(かわむら・ゆうこ)
アンチエイジングをコンセプトに体の中と外から痩身、美容皮膚科をはじめとする様々な治療に取り組む医師。海外の再生医療を積極的に取り入れて、肌質改善などの治療を行ってきたことから、対症療法にとどまらない先端の統合医療を提供している。
保有資格
- 日本抗加齢医学会専門医
- 日本麻酔科学会専門医
- 日本レーザー医学会認定医ほか
